いつもブログをお読みいただきありがとうございます。気がつけば530記事を超えていました。今年に入って週2・3回が発信のペースになっています。今後も同様のペースで続けていこうと思います。よろしくお願いいたします!
\ブログにお越しいただきありがとうございます♪/
自分らしく働きたい女性管理職のために、
日常や仕事の中で得た気づきやヒントを発信しています。
🌸 女性管理職のリアルな声が集まる『女性管理職のためのコミュニティ A lot of flowers』を運営中。
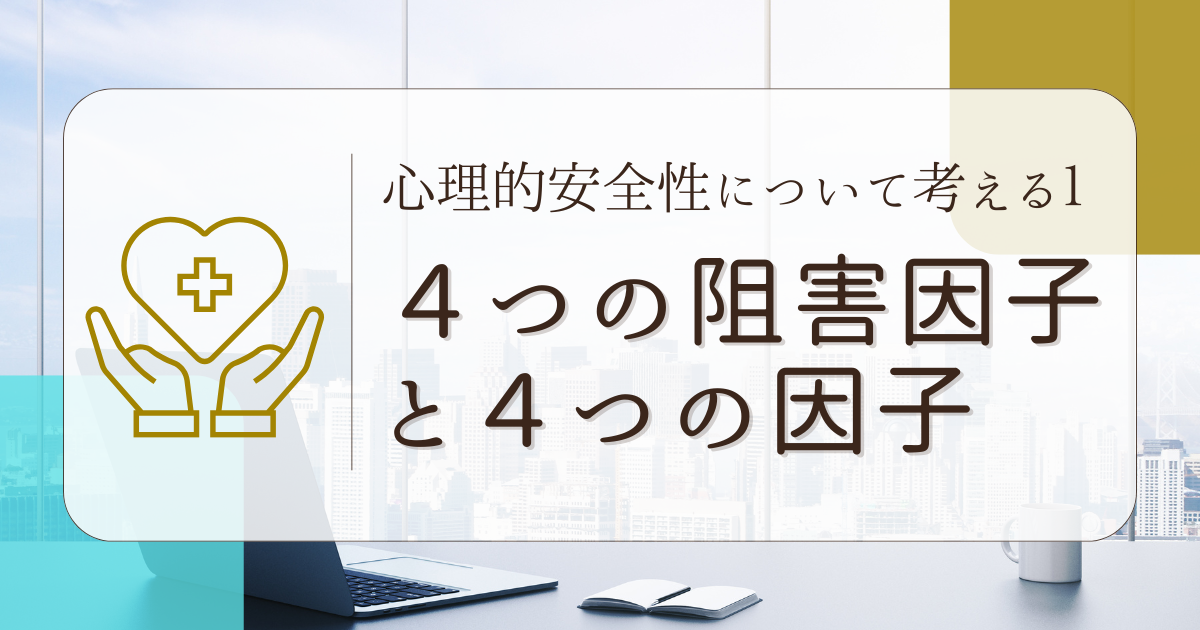
今日は「心理的安全性について考える1 4つの阻害因子と4つの因子」です。
はじめに
心理的安全性という言葉をよく聞きませんか?私が勤めていた会社でも「心理的安全性」と書かれたポスターが数年前から貼ってありました。
職場に心理的安全性を確保するために気をつけるべき点も書かれていました。
今日は、そんな心理的安全性について理解すべく取り上げようと思います。
心理的安全性とは?
チャットGPTの回答はこちら
心理的安全性(Psychological Safety)とは、「このチームでは、率直に意見を言っても罰せられたり、恥をかかされたりしない」という安心感・信頼感のこと。
簡単に言うと、「変なことを言っても大丈夫と思える空気」「失敗や弱さを見せても受け止めてもらえる雰囲気」です。
✔ 起源
1999年、ハーバード・ビジネス・スクールのエイミー・エドモンドソン教授が提唱した概念が元祖です。
✔ 注目されたきっかけ
2010年代にGoogle社が行った「プロジェクト・アリストテレス」で、「成果を出すチームに共通していたのは心理的安全性だった」と発表したことが、世界中で広まりました。
というわけで、心理的安全性という言葉が広がったそうです。きちんと実績があるということが立証されているということでした。
さて、私が心理的安全性をどのように理解していたかというと、「どんなことを言っても大丈夫な場所」でした。
そう理解している私でも「じゃあ、なんでも率直に言っていいのか」というとそうではないと思っています。やっぱり言っていいことと悪いことがあると思っています。
おそらく心理的安全性が保証されている職場でも言っていいことと悪いことがあると思うのです。例えば誰かの悪口に当たるものは心理的安全性が保証されている職場でも言わない方がいいと思いますよね。
ですので、言ってもいい範囲が昔とは変わったということだと思います。
これまで、日本では忖度して言えなかったことなどが、言っても良くなっていると言う理解です。昔なら言わない方が良かったことを言う人が出てくるので、聞く側は嗜めるとか怒るではなくて、受け入れたと思われるような対応をするに変えなければいけないのだと思っています。
心理的安全性を阻害する4つの因子
心理的安全性が低くなるチームに共通する4つの因子は次のとおりです。
1 無知だと思われる不安
2 無能だと思われる不安
3 ネガティヴだと思われる不安
4 邪魔だと思われる不安
具体的に見ていきます。具体例はGoogle検索の際にAIが答えてくれた内容です。
1 無知だと思われる不安
質問や確認を躊躇し、学習機会を損失する原因になります。
「ここでこんなことを質問したら馬鹿と思われるかな?」という不安から、疑問を質問しない。
上司からの指示に対する質問ができないというのが事例です。
私が新入社員の時の話です。
書類にハンコを押すと言う仕事を教えてもらったのですが、同じような書類が3枚繋がっている三連式の紙が回ってきました。3枚とも押すのか、1枚だけ押すのかが分からず。先輩を見るととっても忙しく働いておられて質問がしづらく、「きっとこうだろう」という自分の判断で3枚ともハンコを押しました。しばらくしてから先輩がその書類に気付き、本当は1枚しか押す必要がない書類で間違っていることが判明しました。お客さまにお返しする書類がハンコで汚くなってしまい、お詫びをしたという出来事がありました。
とても忙しくしている先輩に、それぐらい考えたらわかるでしょと言われそうな質問だったので、自分からは声をかけられず、先輩が確認してくれるのを分かっていて、もし間違ってたらその時に気づいてくれるはずと考えていたことを思い出しました。
以降は自分が無知と思われることよりも、仕事を進めることを優先しようと決めたので、聞きづらいことはあっても最終的には確認するようにしていました。ただ、質問するときに知らなくてすいませんという思いはどこかに持っていたように思います。
外資系出身の方が多い場所で働いたことがありますが、そこで働いて居る人たちは分からないことを分からないと素直に言っていたことを思い出しました。申し訳ないという感じもなく、ただ、分からないから聞くというスタンスだったので、感情が浮き沈みせず、淡々と仕事が進んでいっていくような感じでした。
質問することに関して罪悪感とか不要ですね!
優秀な方が多かったので、理解は早かったですし、質問も的確でした。
2 無能だと思われる不安
失敗やミスを報告を避け、成長を妨げる可能性があります。
「失敗したら評価が下がるかもしれない」という不安から、失敗を報告しない。
失敗を報告しないというのが一番避けたいと思っていた私は、常々「悪い報告ほど早くしてね」とお願いしていました。
そして、悪い報告が来た時には「どんとこい!!」という雰囲気を醸し出していたので、ここはスムーズだったと思います。なんともならないミスはありませんから。
自分自身のミスもさっさと表面化させないともっと大ごとになると思っていたので、基本はすぐに報告していました。ミスは隠し通せないものです。
無能とミスは関係ないこともありますし。
3 ネガティヴだと思われる不安
意見や提案を控え、協働を妨げる可能性があります。
「反対意見や批判的意見を言ったら、迷惑がられるかもしれない」という不安から、意見を言わない。
これは往々にしてあると思います。
特にワンマンで決めたがる人の下では意見は言いにくいものですね。私も黙ったことがあります。
私自身の考えでいくと、反対意見を言う方が組織にとって利益になると思えば自分の不利益は横に置いておいて意見をする方がいいと思っていました。
そんな感じでしたから、他チームの上司たちに率直に意見をして生意気だと思われていたことがありました。その上司たちも私の仕事に対する姿勢は認めてくださっていたので、最終的には可愛がってもらいました。
4 邪魔だと思われる不安
改善提案を控え、組織の停滞を招く可能性があります。
他のメンバーに「邪魔」だと思われる可能性のある発言・行動をすること
これは3に通じるところがあると思います。
改善提案をしたら、仕事が増えるので、周りから嫌がられるとか自分に回ってくるので嫌だ、という意見はよく聞きます。
私は長期で見たらい良いことは今が少々しんどくても、未来の誰かへのプレゼントになると思って取り組むようにしていました。それは自分が出した提案が、自分で対処できるという範囲内だったり、そこまで他人に負荷がかからないという範囲だったかもしれません。
ということはやはり、他人に迷惑だ、邪魔だと思われることは言いづらいですね。
改善提案をポジティブに受け入れる土壌と、楽しんで仕事をするという土壌が必要ですね。あと心のゆとりも。
4つの因子
心理的安全性のある会社は、以下の4つがあるチームと言われます。
1 話しやすさ
2 助け合い
3 挑戦
4 新奇歓迎
具体的に見ていきます。具体例はGoogle検索の際にAIが答えてくれた内容です。
1 話しやすさ
自分の意見や考えを安心して伝えられる、また相手の意見にも耳を傾けることができる環境です。
4つの中でも最も重要だと言われているそうです。必要な会話だけをするのではなく、日頃から仕事の会話をしたり、雑談をしたりして関係性を作っておく必要があると言います。
私は絶対に言わないといけないことが言える関係性であれば良いと思います。
上司が報告して欲しい内容と部下が報告した方がいいと思う内容がずれていることがある時はざっくばらんに話ができるチャンスだと思います。こういう、仕事のちょっとした取り違えなんかを話しやすい関係性にしておくと、大きなミスでも話しやすかったり、改善提案がもらえたりします。まずは軽い取り違えから言いやすくするという戦法です。
他にも「〇〇という改善したいと思うんだけどどう思う?」と、部下の意見を必ず聞くようにしていました。これを積み重ねることで改善提案をしてくれるようになりました。あとは、こちらから話しかけた後に、部下にたくさん話してもらうということも心がけていました。上司に話すという機会が多いと咄嗟の時でも話しやすいと思います。
2 助け合い
メンバーがお互いをサポートし、困難を乗り越えるために協力し合う精神です。
同じメンバーで争うことをしない方がいいと書かれています。蹴落としたりするのではなく、協力して目標に向かって頑張っていくという意識を持つことが大切だと言います。
営業なんかでは、チームでありライバルという関係性だったりするので、サポートしていることを評価に織り込んでいくということが大切だと思います。
協力し合うと言いますが、本当に対等に協力し合うという関係性を作るのは無理です。誰かがたくさんサポートをして、誰かがたくさんサポートをされます。それをサポートして損したと思わせないような評価や制度、声かけ等の配慮が管理職には求められると思います。
3 挑戦
失敗を恐れずに新しいことに挑戦し、失敗から学び成長していく姿勢です。
新しい挑戦に対して、失敗しても責められたり馬鹿にされたりしないということだそうです。
新しい挑戦をするときに、誰を味方につけているかということが大事かなと思います。自分だけのチャレンジにせず、できるだけ味方を多くしてチャレンジすることで仕事がより楽しくなり一体感も生まれると思います。
4 新奇歓迎
新しいアイデアや意見を歓迎し、多様な考え方を尊重する姿勢です。
従来と違うアイデアが出てくると「うっ」と思うことはあります。「それは違うでしょ」と出かかることもありますし、表情や雰囲気で「違う」ということを醸し出したりすることもあったと思います。
ですが、一瞬「うっ」となってもいいと思うのです。その後、その意見が本当に受け入れられないかどうかを考えたり、受け入れてよくなるとしたら?という問いを持ったりすることで、受け入れる素養ができてきます。
大阪都構想はおぼえておられますか?結局は叶いませんでしたが、最初に都構想と言った時には「何言ってるの?」と思っていた人たちも何回も聴いていれば「都構想」もありかもしれないと思っていく。
そういう環境を自分自身で作っていくということをやっていけば、どんどんと新しいアイデアを受け入れることができると思います。
最後に
さあ、たっぷりと心理的安全性について書いてきました。
チームの環境というのはやはり、チームのトップの影響を大きく受けます。チームのトップが体現しているとみんなはやりやすいですね。
一方で、どんな環境でも心理的安全性が高い人と心理的安全性が低い人がいます。どんな環境でも心理的安全性が高い人はチームの活性化剤になってくれますので、重宝すると思いますし、言動を見習うところも多いと思います。
心理的安全性が低い人にはあまり無理にオープンにさせない方がいいと思います。みんながオープンになっていくに従って自然とオープンになっていくことを期待するのがいいかなと思います。あとは、相手が嫌がらないぐらいに意識して話しかけるという努力でしょうか?
では今日はこの辺で。
最後までお読みいただきありがとうございました!
❀ 𖤣𖥧𖥣 * … * … * 𓂃𓈒𓏸◌ ❀
女性管理職のためのコミュニティA lot of flowers は、 業種や肩書きの違いを越えて、どんなリーダーシップも認め合い、応援し合える場です。
✉️ **無料メルマガ**(月曜朝5時配信)
分析・本質派の私つっきーと、寄り添いのゆっきーをはじめ、管理職のサポートのプロたちが週替わりで綴っています。
→ [メルマガ登録はこちら]
▶︎ [公式HPはこちら(イベント情報・お申し込みなど)](https://www.reservestock.jp/page/index/47293)
▶︎ [コミュニティ紹介記事はこちら]
---
📩 **個別相談・体験会のご案内**
「ちょっと話してみたい」「詳しく聞いてみたい」という方へ。
オンラインでの個別相談は随時受付中です。
→ [体験会のお申し込みはこちら]